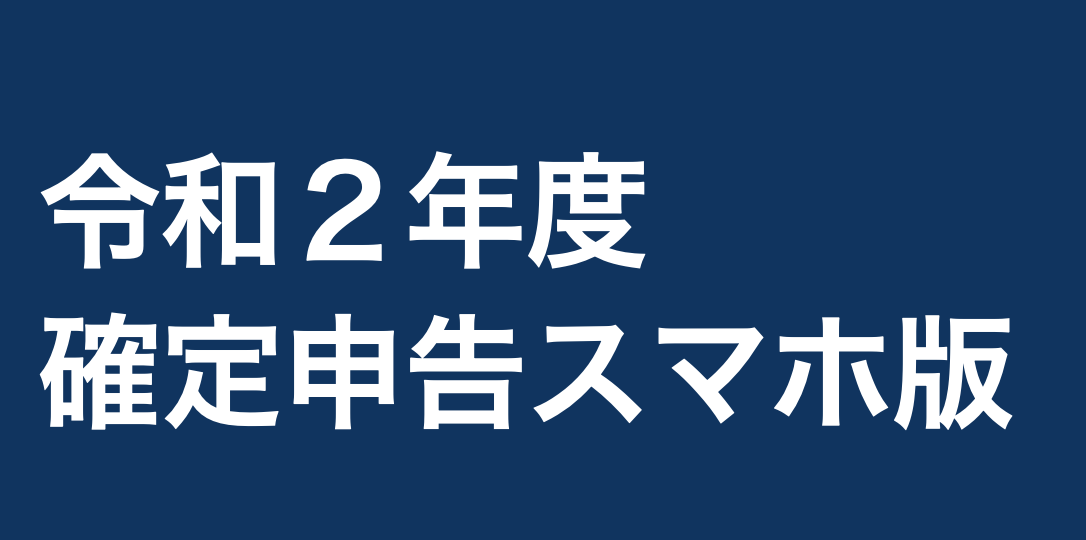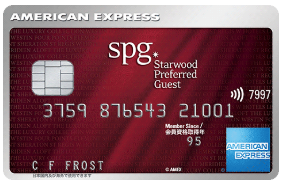予定では、チビは男の子なので(あくまで予定ですが…)
心構えを兼ねて読んでみました。
amazonのレビューもよかったので、こちらと、もう一冊ありますのでそれは次の機会に投稿します。
http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?t=yakko0a-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4872904451&nou=1&ref=qf_sp_asin_til&fc1=000000&IS2=11=_blank&m=amazon&lc1=0000FF&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr
kozyは男ではないので、やはり男の子の気持ちは今一つわからないのが本音。
職場は超男社会なんですけどね。
本書を読み進めていくと、意外にも大人の男性にも共通する点が多々ある気がします…。
ははは
著者の諸冨氏は教育カウンセラーで、過去の出版は100冊を超えるようです。
女の子の育て方という本も出しているそうな。
具体的なフレーズまで掲載されているので、スッと頭に入ってくる本でした。
この本をベースに、少し夫婦で話をしておかねばと思います。
下記、一部ですが備忘録として掲載いたします。
・お母さんとのラブラブが男の子の自信を育てる
①ラブラブ期:0~6歳くらいまでの、いわゆる乳幼児期(生まれてから幼稚園・保育園まで)
②しつけ期:6歳から12歳までの、いわゆる児童期(小学生時代)
③見守り期:10~12歳以降、18歳くらいまでの、いわゆる思春期(小学校高学年から大学生くらいまで)
→しばらくはラブラブ期なんですね。
・勇気がある男の子の定義
困難を克服しようとする
失敗しても、自己嫌悪に陥らない
できるかわからないことにチャレンジする
自分1人だけでやろうとせず、人と協力しようとする
・してほしいことは命令口調ではなくお願い口調で
一歩下がって
ポジティブに
具体的に
・ほめるとき
①すぐその場で
②目を見て
③頭をなでながら(10歳くらいまでなら効果ある)
→部下を褒めることとも少し似ているような…。さすがに頭は撫でませんが^^;
・お手伝いが将来を決める(5歳までに習慣化させる。2歳の子でも、ごみ箱に捨てるという行為はできる)
男の子を、まっとうに就職して働き、結婚できる「一人前の男」に成長させるために、家事のお手伝いをさせることが親として重要な、やるべきこと。
就職活動に熱心な男子学生には、小学生のころに、家事のお手伝い(風呂掃除、料理など)をした経験という共通点がある。
お手伝いをすることでつく3つの力
①フットワーク力がつく:体を動かして働くモードが身につく
②役割を果たす喜び、みんなの役に立つ喜びが体験できる:働くことで自分の価値を実感したい
③困難に立ち向かう力を育てることが出来る:自己貢献感(ぼくは人の役に立てる存在)という自信は、彼らが将来様々な困難を乗り越えていく原動力になる
→お手伝いは、勝ち負けや失敗を気にせずに、自信を育てていくことができる絶好の機会である。子どもは、親の喜ぶこと、役に立つことをするのが大好き。
・お手伝いの注意点
①失敗するのを前提に頼む
②失敗しても起こらない、イライラをぶつけない。やりなおしたんだから、、などと子供の前で言わない。どうせ役に立たないんだ、と思わせない。「あらら、びっくりした?大丈夫、今度はうまくできるといいね」等。
③失敗したあとの片付け方を教え、正しいやり方を考えさえる。「どうすればうまくできたかな?」「今後はどうすればいいと思う?」
④たとえやり直しても、子どもには言わない。「お母さんがやり直しておくからそのままにしておいて!」は、NG!
・アサーションな会話ができる家庭を築く
※アサーション:相手の立場に立ちながらも、自分の気持ちをうまく伝えていく方法。自分も相手も大切にしながら(何とか)うまくしのいでいける。多少傷ついても時がたてば気まずくなった相手とも関係を修復できる。人間関係を切り抜けていくために必要なタフなスキルが身につく。
いやなことはいやだ!と言う練習をする。
×「いつまでゴロゴロしているの!怒」
○「お父さん、仕事で疲れているのはわかるけど、少しだけ家事を手伝ってくれるととても助かるな」
→アサーション、という言葉はこの本で初めて知りましたが、とても良い考え方ですね。女性はちょっと苦手なようです。kozyもこんな風に育ててもらいたかった。笑
やはり、人間なのでその時になるとイライラすると思うのですが、アサーションを忘れないように、根気強くできればいいですね。
図書館で借りたのですが、0歳でおそらく忘れてしまいそうなので、バイブルとして買っておこうかな…と検討中の一冊です。
お時間があれば、是非クリックお願いします^^
ほかの方のブログもたくさん見れます♪

にほんブログ村
![]()